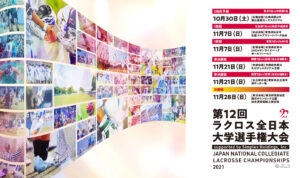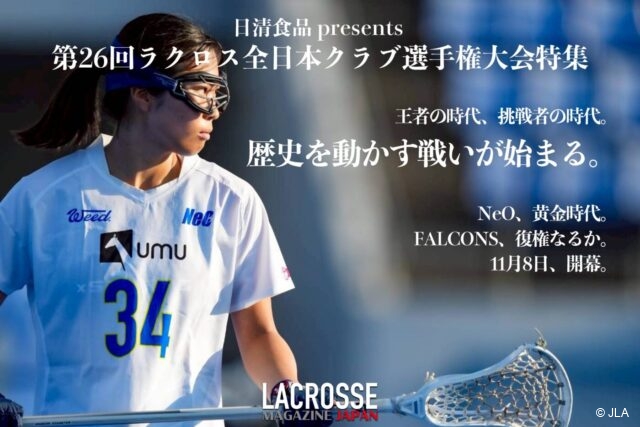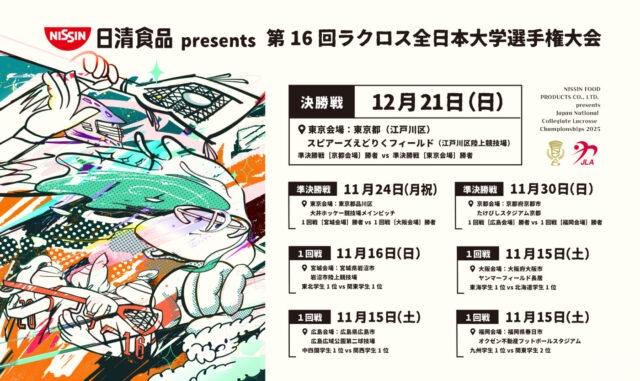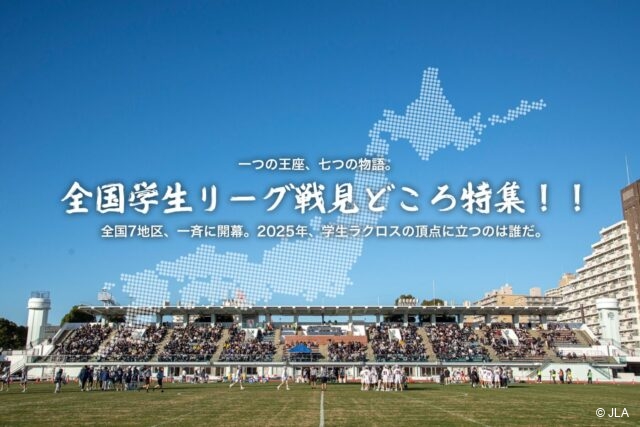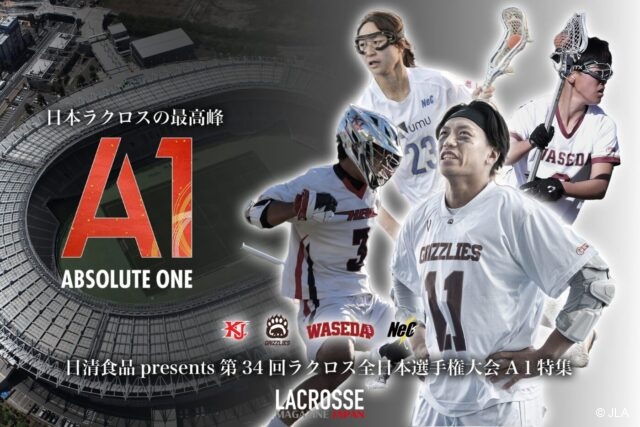Columnコラム

ラクロスの試合を支える存在――それが審判員です。学生時代に笛を吹き始めても、社会人になると仕事や生活の変化により、多くの人が審判活動を続けることを難しく感じます。しかし一方で、社会人になってからもフィールドに立ち続ける審判員がいます。この企画ではそんな審判員たちにインタビューし、「なぜ社会人になっても審判を続けるのか」、そして「審判の楽しみ方」を掘り下げていこうと思います(全4回)。
第2回 会いたい人に会える場所~古戸奏江さんの場合~
古戸奏江さんは、2025年3月に名古屋大学を卒業して、クラブチームには所属せずに審判員を続けています。前年2024年度には、学生審判員としての取り組みが評価され、審判功労賞を受賞しました。東海地区の学生審判員の課題と社会人になっても続ける理由をお聞きしました。
「派遣班」に選出
「派遣班の一員に選ばれてとても嬉しかったです」。古戸奏江さんは、大学4年生のときに派遣班の一員に選出されました。派遣班とは、リーグ戦・新人戦など公式戦へ審判員を派遣するために募集から決定までを行う班のことです。派遣班に選ばれることが名誉なことなのか、仕事が増えて困ることなのか。お聞きすると古戸さんは、すぐさま「嬉しかった」と答えてくれました。「東海地区だけかもしれないのですが、派遣班には毎年4年生が4人選出されます。先代の派遣班だった審判員が、次に4年生になる審判員のなかで審判に対して意欲的だったり、活動に興味があったりする人を選んで声を掛けます。派遣の仕事を任せてもらえるということは、審判のグループのなかで評価されているんだと思えて嬉しかったです」。
2024年度東海地区学生リーグ戦で笛を吹く古戸奏江さん
審判員がいるのに埋まらない
「審判員がこれだけいても埋まらないんだなぁ」。古戸さんが派遣班になって直面したのが、埋まらない派遣表でした。大学2年で審判資格を取ってから、4年生で派遣班になるまでは気づかないことでした。誰かが埋めてくれるものだと無意識に思っていた。その「誰か」に自分がなったときに、古戸さんは苦労を経験します。「まずは、東海地区の審判員全体へ呼びかけるのですが、それでも足りなければ、LINE公式アカウントを活用し、審判部の方の人脈を借りながら直談判しました」。古戸さんは派遣班の仕事を通して、平日のリーグ戦に入ることができる学生審判員を増やす必要性をより一層感じました。
学生審判員を増やさなくては
東海地区の審判員の内訳は、2025年度公式戦において「社会人42名」、「学生 33名(うち5名が2025年度3級合格者)」。実際に公式戦で笛を吹いた審判員は、「社会人26名」「学生21名」(2025年9月現在)。社会人審判員が充実している反面「東海地区は学生審判員が少ない」ということが課題になっていると古戸さんは指摘します。学生審判員が少ないことで困ることの一つが、社会人審判員が仕事をしている平日開催の公式戦への派遣です。「学生審判員は自身が所属する大学チームの練習を優先します。練習を抜けられなくて派遣に入ることができないという学生審判員が多いのです」。2024年度東海地区学生リーグ戦の参加校15校のうち、審判員がいないチームは約半数ありました。学生審判員を増やしたい。当時大学4年生だった古戸さんたちが開催したのが「審判の重要性を伝える会」でした。
審判員がいることのメリットをプレゼン
「審判員に興味を持ってもらうために、審判員がチームにいると、こんないいことがあるよというメリットをプレゼンしようと思いました」。古戸さんは近い年代の審判員と一緒に「審判員の重要性を伝える会」を作り学生チームへ向けてプレゼンすることにしました。学生連盟のほうからチームに審判員の重要性を知ってもらう会を開きたいと依頼もあり、12月に開催された主将会に時間を設けてもらいました。「発信しないと興味を持ってもらえない。そもそも、審判員が足りていないことが知られていない。足りてないから増やしたいでは伝わらないから、まずは、審判員がいることのメリットを伝えようと思ったんです」。
古戸さんたちが作成したプレゼン資料の一部(4ページ目)
古戸さんたちが作成したプレゼン資料の一部(5ページ目)
行動に移せるように工夫
「審判員の重要性を伝える会」をただ聞いてもらうだけの会にしたくなかった古戸さんたちは、プレゼンのあと、3チームずつ分けて、自チームの課題を炙り出し、どんな行動を取れば解決するのか話し合う時間を作りました。話し合う時間を設けたのは、チームによって審判に対する課題が違うからです。例えば、チームスタッフの審判員はいるがプレーヤーの審判員がいないチームには、プレーヤー審判員がいることのメリット。プレーヤー審判員はいるが誰もリーグ戦で笛を吹かないチームには、リーグ戦で吹くことで得られるメリット。審判員が一人もいないチームには、審判員がいるメリットなど、チームの課題によってアプローチ方法が違ってきます。会のなかで、そのチームが審判員を増やし、活かすためにはどういう行動をしていけばいいのか考えることができ、古戸さんたちは手ごたえを感じました。ただ、後日チームに戻って、本当に行動に移せたかどうかまで、古戸さんたちは確認することができません。「会のなかで、『これまで希望者しか4級試験を受けさせてなかったけど、これからは全員受けさせます』と言ってくれたチームもありましたが、その後どうなったかはプレゼンをするだけのわたしたちには分からないんです」。主将会が12月開催であるため、2月の4級審判試験まで時間が空いたことも実際の申し込みや受験数の増加に繋がらなかったかもと古戸さんは分析し、今後も「審判員の重要性を伝える会」を続ける必要性を感じています。
(Lacrosse Magazine Japan編集部より)
ルールの勉強をしてプレーに活かしてみませんか?次回女子競技4級の審判試験は2026年2月8日(日)です。詳細はこちらです
【お知らせ】2026年 公益社団法人日本ラクロス協会公認 新規審判員試験(女子競技4級、男子競技3級)のお知らせ | JLA | 公益社団法人日本ラクロス協会
ゼロだったチームに審判員が誕生した
古戸さんは審判員がいないチームに審判員を新たに誕生させることにも関わりました。「審判員がいないチームのなかから3人ほど審判に興味がある子がいたので、わたしとグループLINEを作って、資格試験のスケジュールを立てるお手伝いや技術向上のための相談を受けるなど、メンターをして、新たに審判員が3人誕生しました」。
新規審判資格に合格した中京大学3年生(2024年当時)谷川莉菜さん (左) と古戸奏江さん(右)
チーム東海、チーム審判という居場所がある
社会人になってクラブチームに所属しない場合、審判員としての帰属意識というのは生まれるものなのか。生まれにくいから社会人になったら続ける人が少ないのか。そんな疑問を古戸さんにぶつけてみました。「帰属意識はすごくあります」。古戸さんははっきりと答えました。「チーム東海」、「チーム審判」としての居場所がしっかりあるというのです。東海地区に所属するJLA公認審判1級であり国際審判員である阪本一美(さかもとひとみ)さん、宮崎彩(みやざきあや)さん、小鹿えりか(おじかえりか)さんといった先輩審判員が「チーム審判」を作ってきたのです。「東海地区は1級や2級の審判員の方々が温かく、審判員全体で仲がいいんです。わたしが試合に入るのも審判員の友達、先輩方に会いたいからです」。試合会場に会いたい人がいる。それこそが「帰属意識」ではないか。社会人審判員が42名もいる理由はそこなのだろうと思えました。「東海地区初期のころからいらっしゃる審判員さんがこれまで居場所を作ってきてくださり、ラクロスや審判を通してその方々と交流できることがわたしが審判を続けている理由になっています」。東海地区の「チーム審判」にあるのは温かさだけではありません。「もっと成長していかなければという思いも持たせてくれるのが東海地区審判です。1級審判員の方々のすごいところは、ただルールブックの文言に従って試合を運営するのではなく、安全と面白さとの両立をどう試合で実現できるか、ルールブックの文言を自分なりに解釈して落とし込んでおられるところです。プレーヤーと一緒にラクロスを作っているのだとおっしゃって、すごく素敵な考え方だと思いました」。
他地区審判員との交流
他地区審判員との交流。2025年6月のスーパーカップにて
古戸さんは社会人審判員になってからも、他地区審判員との交流する機会を持つようにしています。今年(2025年)は6月に行われた「第14回 女子ラクロス・スーパーカップ」へ審判員として参加しました(大学生のときはチームスタッフとして参加し、審判員は合間に行っていました)。試合以外では、全国の審判員向け資料を作成する現場に立ち会いました。「どちらもすごく刺激になりました。というのも、どちらも年代層が近い人と関われたため、同期なのにこんなに審判が上手なんだ、と思えたり、こんなに考えているんだと思えたり。東海地区も審判がうまい人はいますが、他地区にもすごくうまい人がいて、刺激になってもっとうまくなりたいと思えました。資料作りでは、仕事がとても忙しい方が、『ラクロスをよくするために、もっとルールをこうしていこうよ』という強い思いを持っておられて、それに触れてラクロスの関わりがより深まり、もっと熱意が高まりました」。
マイナースポーツだからこそ面白い
古戸さんのお話を聞いていると、「こんなに審判員ライフを楽しんでいる人がいるんだ」と聞いているこちらが嬉しくなりました。社会人審判員は楽しいものだともっと伝えたい。社会人になったら審判をしようか迷っている学生や、来年はどうしようか迷っている社会人へ古戸さんの続けている個人的な理由を教えてほしいとお願いしました。「わたしは、プレーヤーとか審判とか関係なくラクロスに携わっている人が好きなんです。ラクロスには、日常とは別で高い目標を持って頑張っている人が多い。自分はこういう人になりたいという像をすごく高く見ている人が多い。そういう人たちと一緒にいると自分もまだまだ成長していけるなと思えます。技術だけじゃなく人間性の部分でも努力ができる場。そんな場所は社会人になればなるほど少なくなるんじゃないでしょうか。だから、何かを頑張って達成する機会を得るために、成長性を自分の力で感じられる場を持つためにラクロスに関わり続けたい、審判を続けたいと思っています。ラクロスは日本のなかでもどんどんルールが変わっています。それは、ラクロスがマイナースポーツだからこそで、どうしたらラクロスがより面白くなるのかを模索しているところだからだと思うんです。より多くの人たちにこのスポーツを面白いと思ってもらいたい。そのためにはどんなルールにしたらいいのか模索するところに関われるというのはマイナースポーツの醍醐味だと思っています。野球やバスケットボールといったメジャーなスポーツだと、トップチームの選手に会いたくても会えない。1級審判に会おうと思っても遠い。でも、ラクロスだと1級審判が試合会場にいて、話ができて、相談に乗ってもらえて、アドバイスまでもらえるんですよ。すごい世界だと思います。成長の幅も広くて、刺激的な環境がラクロスであり、審判員だと思います。だから、審判員をぜひ続けて極めてもらいたいです。そうしたら、とても楽しいんじゃないのかなと思います」。
プロフィール

- 名前:古戸奏江さん
≪ スタッフ歴 ≫
- 2021年~2024年 名古屋大学ラクロス部(女子) マネージャー
≪ 審判員歴 ≫
- 2022年~ 審判員(3級)
- 2024年~ 審判員(2級)
写真提供:古戸奏江さん
Text by 日本ラクロス協会広報部 岡村由紀子