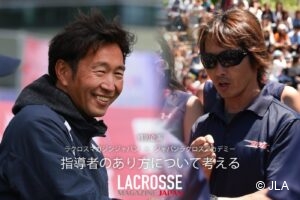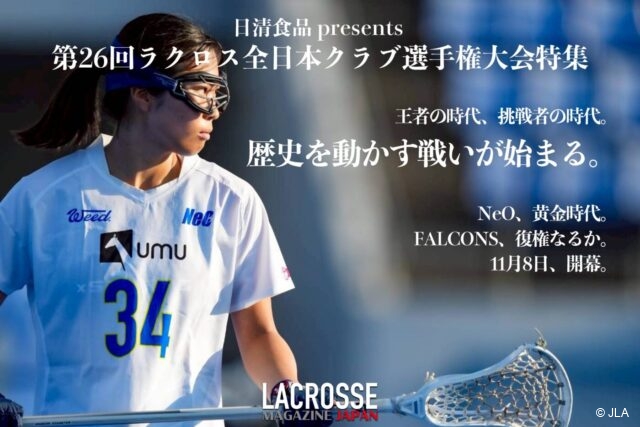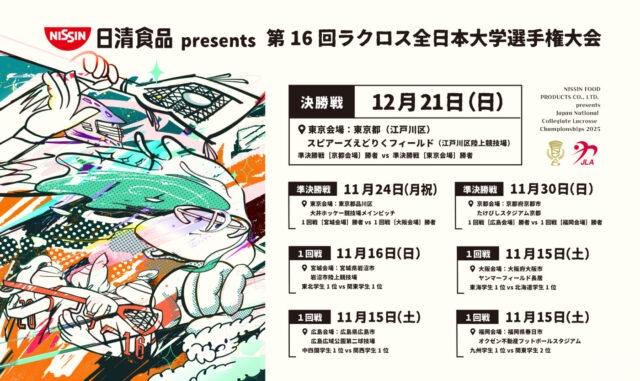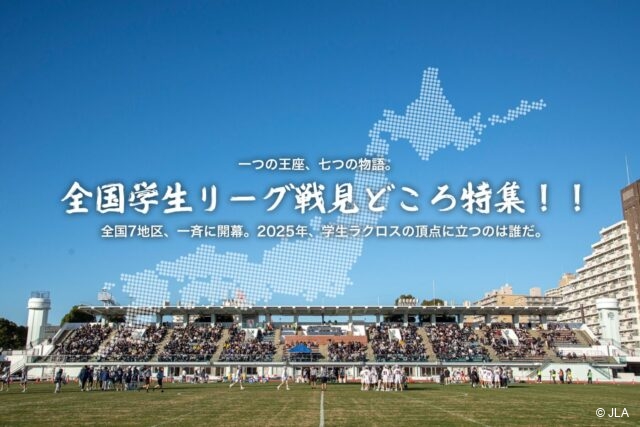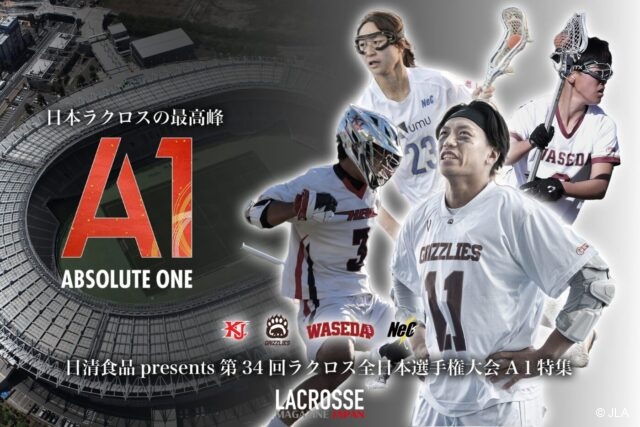Columnコラム
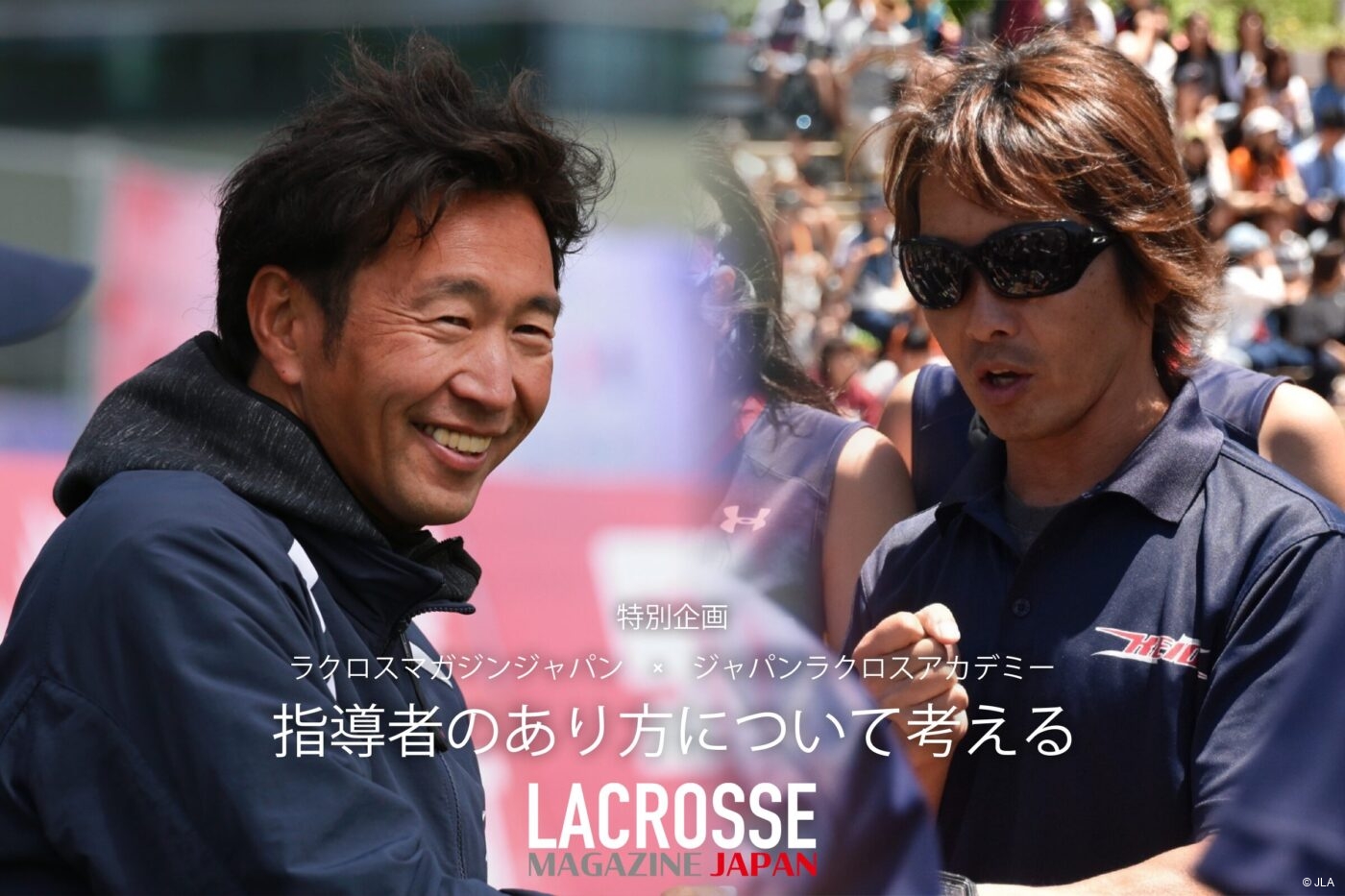
2022年7月、アメリカ・アラバマ州バーミングハムで行われた「The World Games 2022」。SIXESフォーマットで開催された本大会において、男子代表は年齢制限のない大会で史上初の銅メダルを獲得しました。
さらに先日行われた The World Games 2025 での女子代表の活躍、男子U20世界選手権での成果、そして2026年・2027年に日本で開催される男女の世界選手権を控え、日本ラクロスは今、世界的に注目を集めています。
こうした状況の中で、選手はもちろんのこと、その選手たちを指導する「指導者」の存在について考えていくことの重要性も大きくなっていると感じます。今回のテーマは「これからのラクロス指導者は何を考えるべきか」。日本ラクロスにおける指導者の基盤を築き、支えてきたお二方にお話を伺いました。
登場人物
大久保 宜浩(日本ラクロスアカデミー:JL Academy)

<指導歴>
- 1994年 男子フル日本代表アシスタントコーチ
- 1996年 男子19歳以下日本代表ヘッドコーチ
- 1998年 男子フル日本代表ヘッドコーチ
- 1999年 女子19歳以下日本代表テクニカルアドバイザー
- 2001年 女子フル日本代表ヘッドコーチ
- 2009年 男子22歳以下日本代表テクニカルアドバイザー
- 2010年 男子フル日本代表ヘッドコーチ
- 2014年 男子フル日本代表ヘッドコーチ
- 1998年 関東地区ユース選抜(男子)ヘッドコーチ
- 2008年 関東地区ユース選抜(男子)ヘッドコーチ
- 1997〜1998年 慶應義塾高等学校ヘッドコーチ
- 2000年〜 慶應義塾大学(女子)ヘッドコーチ
佐藤 壮(日本ラクロスアカデミー:JL Academy)

※指導者歴は別途詳細追記予定
佐野 清(ラクロスマガジンジャパン編集長)
<選手歴>
- 2022年 SIXES男子日本代表
- 2023年 男子日本代表
<指導歴>
- 2022年 男子21歳以下日本代表アシスタントコーチ
- 2022年〜 東北大学男子ラクロス部
- 2024年〜 慶應義塾大学男子ラクロス部
日本ラクロスアカデミーについて
大久保:私がラクロスを始めたのは、日本にラクロスが導入されて間もない頃だったので、指導者というものは存在しませんでした。卒業後もしばらくは指導の制度らしいものはなく、OBやOGが時々練習に顔を出しては指導のようなことをしていた、という状況が続いていました。その熱意が選手に伝わらず、とても勿体ないことだと感じていたんです。
大久保:私自身、当初は指導者を目指していたわけではなく、誰も指導者がいない現状から指導者にならざるを得ない状況でした。そんな中、当時のJLA理事方でサッカーの指導者育成に携わっていた方がおられ、その方から「指導者の責任」について多くを学びました。そして、日本のラクロスが世界の場で結果を残していくためには、もっと指導者育成に力を入れる必要があると考えるようになったんです。それが「日本ラクロスアカデミー」を創設する大きなきっかけでした。
佐野:アカデミーをつくるにあたって、参考にしたスポーツなどはあったのでしょうか?
大久保:これは私の性格とも関係していますが、他と同じことをするのが嫌いだったんです(笑)。ラクロスは他のスポーツでうまくいかなかった人や、新しいことに挑戦したい人が集まるスポーツでした。だからこそ、新しいアイデアが次々に生まれる。私はそうした価値観を大切にするように指導者と関わってきましたし、それが制度にも大きく反映されていると思います。
佐藤:ラクロスは常に正解が変わっていくスポーツであり、試合の中で多くの選択を求められる競技です。だからこそ、与えられた正解に従うのではなく、自分が選んだものを正解にしていく。そして、その過程を楽しめる世界であってほしいと思っています。
日本ラクロスアカデミーが抱えている課題
佐野:私もアカデミーの指導者講習を受けたことがあるので、その感覚はとても伝わってきます。そんな中で、アカデミーが抱えている課題はありますか?
大久保:一つは「正しい知識」「正しい技術」をどう扱うかという点です。知識というのは絶対的に正しいものは存在しないと思っています。ただし、一般的に言われていることはある程度伝えなければならない。一方で、技術論は時代背景や道具の変化、さらにはルールの変更によっても変わっていきます。
大久保:けれども「正しい技術の教科書」を求められる場面は非常に多い。なぜ出さないのかと問われることもしばしばあります。アカデミーの講義では、必要以上に技術指導や戦術の話に踏み込みません。「この投げ方が正しい」「この取り方をしなさい」といった指導は、むしろ成長の機会を奪うこともあるからです。
大久保:もし協会が「これが正しいラクロスです」と定めてしまえば、大学やクラブは独自の工夫をする余地を失い、日本全体のラクロスの発展を妨げかねません。各チームが「自分たちこそ正しい」と切磋琢磨する環境があってこそ成長が促される。それこそが指導者自身の成長の楽しみだと思っています。しかし現場からのニーズとアカデミーの理念の間には、常にジレンマがあるのです。
佐野:確かに、コーチとして試行錯誤しながら自分なりの答えを見つけていくことは、どれもかけがえのない経験です。一方で、何もないところからは何も生まれない。底上げのために、ある程度ベーシックな技術や考え方も必要ではないでしょうか。
佐藤:それもその通りだと思います。
佐野:私は他大学のコーチ同士でディスカッションをしたり、海外のコーチが公開している戦術や考え方の動画で勉強したりしていますが、それがとても役立っていると感じます。
指導者講習会の様子
佐藤:指導者自身の成長には、やはりディスカッションが不可欠です。海外のコーチサミットや動画も有益ですが、実際に議論し合うことで得られるものの方が大きい。プログラムでも専門家の講義は設けていますが、最も成長につながるのは自分の言葉で疑問を投げ合い、議論する時間です。それで良いのだと、きちんと伝えていく必要がありますね。
大久保:今後の展望としては、資格認定型の講習に加えて、特定のテーマに絞ったカリキュラムを充実させたいと考えています。戦術に特化して繰り返しディスカッションする場や、技術に焦点を当てた実地講習などです。
佐藤:アカデミーはこれまで「資格を付与する講習所」としての性格が強かった。しかし今後は資格を持つ指導者が増えるにつれ、互いに刺激し合い、研鑽を積む場に変わっていくはずです。資格に有効期限を設けて数年ごとに再受講を義務づけているのもそのためです。指導者同士が競い合い、学び合う――そのような場をつくることこそ、これからのアカデミーの役割だと思っています。
ラクロスの外の世界とのつながり/ジュニア世代の指導と文化の継承
佐野:ここまでアカデミーの仕組みを伺いました。では、今の日本ラクロスにおいて特に課題だと感じている点はありますか?
大久保:今だからこそ気をつけなければならないのは、ジュニア世代が増えてきていることです。指導に携わる人の中にはラクロス経験がない方も多く、他競技の経験を持って入ってくるケースが増えています。それ自体は悪いことではありません。ただし、ラクロスが大切にしてきた歴史的背景や「自由度の高い指導」の文化を理解していないと、強い言葉やハラスメント的な指導が入り込んでしまう可能性がある。そこに危機感を持っています。
大久保:世界大会やオリンピックを控え、ラクロス未経験の方からの注目が集まればさらに様々な文化や価値観が流入してきます。そのときにラクロスの文化が弱まったり、消えてしまったりすることは避けたい。だからこそ「ラクロスらしさ」をどう守り、どう継承するかが重要となります。
「考える自由」と「教わった感」の矛盾
佐野:他のスポーツとのギャップも指導に影響しているのでしょうか。私自身、野球や柔道を経験しましたが、指導の感覚には大きな違いがありました。
大久保:ラクロスの良さは「選手が自分で意思決定できること」。だからこそ考え、責任を持って選択できる。この自由さは絶対に失いたくありません。ただ、自由度を高めると「緩い」「教わっていない」と捉えられることもあります。アカデミーは「教える」立場にある一方で「自分で考えなさい」とも伝える。その矛盾は常に抱えています。
佐藤:そこが一番難しい点です。指導者育成の目的は「正解を教えること」ではなく「選択肢のある環境を整えること」。私たちが「これが正しい」と決めてしまえば、選手や指導者が考える余地はなくなってしまいます。失敗してもいいから試行錯誤する。議論しながら成長していく。その過程こそが、指導者にとって本当の学びだと思います。
大久保:だからこそ、アカデミーの使命は「観察し続けること」だと考えています。日本のラクロス文化や環境を見極め、必要なら柔軟に変わる。それ自体がラクロスらしさでもあります。大切なのは「常に正解を探し続ける姿勢」と「選択できる自由を守ること」。指導者がその最前線に立ち続けられるような環境をつくることこそ、アカデミーの存在意義だと思っています。
次回は、これからの指導者の在り方や、指導者としてどう上達するか、などについてもっと掘り下げていきます。