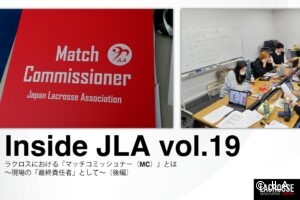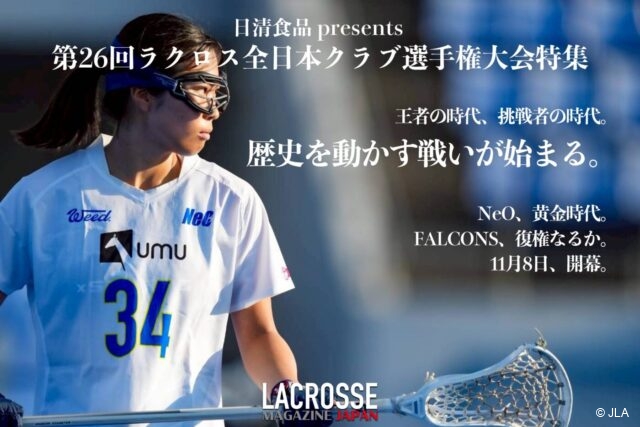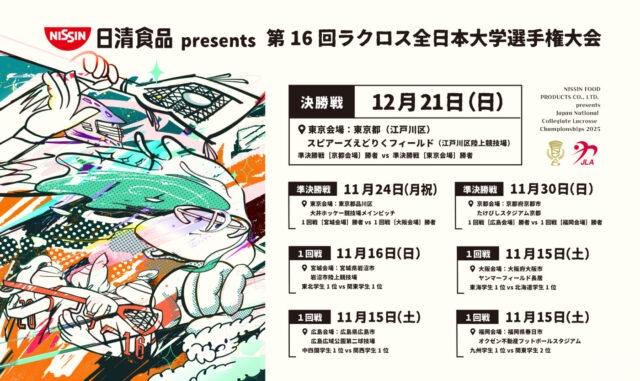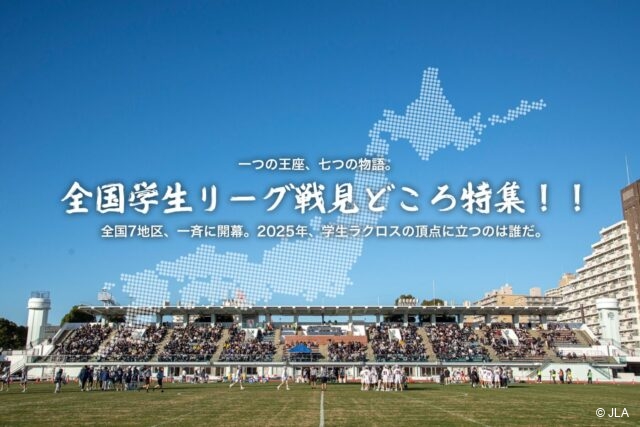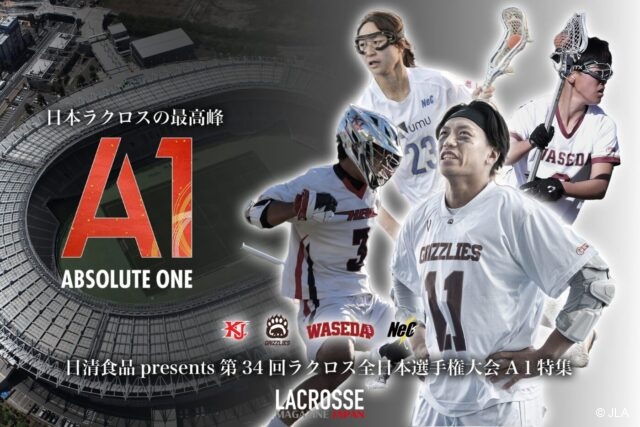Columnコラム

未来へ繋ぐ、私たちの物語(ストーリー)
vol.1|「当たり前」ではない、この熱狂を。
公益社団法人日本ラクロス協会理事 永田久美子
すべての始まりは「場づくり」との出会い:「場」はそこにあるのではなく、誰かが作っている
日本ラクロス協会の運営にボランティアとして携わるようになって18年になる。理事になってからすでに8年目だ。「なんで私ってこんなに働いてるんだっけ?」という疑問も、しばしば頭をかすめる。本稿のテーマは、その問いに対する私にとっての答えであり、JLAの文化でもある「自分たちの遊び場は、自分たちで作る」についてである。
話は18年前に遡る。私は京都大学女子ラクロス部の出身で、学生連盟の大会委員会に入っていた。関西の大会委員会は全ての大学から2年生の班員が出てリーグ戦の運営に参加し、班長については3年生の「有志」が残るというシステムであるが、我が部では私の先輩方も、そして後輩たちも、代々「有志」として班長に残ってきた。「自分たちがリーグ戦に参加するからには、そのリーグ戦を自ら運営する私たちであろう」というのが、我が部の大会委員の系譜だった。私自身は当初「うちの大学からは残るものだから」という理由でなんとなく班長に残った気もするが、それが私にとって初めての、そして本当の意味での「有志」つまり「ボランティア(自主的な全体への貢献)」だった。
結果的にこの大会委員会班長としての経験が、その後のラクロス人生を大きく変えた。
人が集まって、ラクロスをする場。学生連盟で働く前は、その「場」は当たり前に「在る」ように見えた。しかし実際には、誰かがかなり苦労して「作っている」。その場を用意することが、どれだけ大変で、どれだけの人に支えられていて、どれだけ尊くて、どれだけ価値があることなのか。私は班長の仕事を通じて知った。そもそも「場」がなければ、ラクロスはできないのだと。そんなシンプルで当たり前のことを、その時に初めて、肌で感じ、腹に落としたのだった。
そして、その時から、私はずっと「場づくり」をやっている。
私が試合をするとき、いつも誰かがその「場」を作っているのだから。
誰かが試合をするとき、私がその「場」を作る人であろう、と。
仲間と作る「みんなの遊び場」:クラブ連盟で芽生えた、支え合う喜び
「場づくり」の中で長く携わって思い入れがあるのは、関西のクラブ連盟の仕事である。クラブリーグに選手として出場しながら3年間、引退して名古屋に転勤しても出張のような形で5年間、2012年からの合計8年間を役員として働いた。特に選手と両立していた時期は、週5日会社で働き、週2日練習をして、そのあとに連盟の仕事をしたり審判にいったりという生活で、まともな休みがなく、凡人にはかなりきつかった。
やらなくていいなら、正直あまりやりたくはない、だけど、誰かは必ずやらなければならない。社会人になっても休日をつぶしてラクロスを続けているみんなにとって、その成果を発揮する「場」がもちろん必要なのだから。
クラブ連盟の仕事を長く続けられた理由には、社会人のプレーヤーたちを同じ選手として応援したい、という気持ちと、連盟執行部の「場づくり」に献身的な仲間たちを支えたい、という気持ちが大きかったように思う。なんせ、私がいても結構大変なのに、私が抜けるともっと大変なのだ。誰かがやらなければならないとき、「私、MC入りますよ」「俺、備品車出しますよ」そういって一緒に引き受け合ってくれる仲間の存在は、それだけで働く理由になるくらい、嬉しくて、愛しかった。この頃から私にとってJLAの仕事は、「自分のための遊び場を自分で作る」というよりは「みんなのための遊び場を、仲間と作る」という意味をおびるようになっていった。それで、自分自身が引退してからも、名古屋から関西に通って運営を続けていた。
2018年 クラブ連盟西日本支部執行部
審判員への尽きない敬意――「当たり前」ではないということ
ラクロスの「場づくり」に深く関わっていて必要なものを連盟以外に挙げるならば、それはもちろん審判員である。私が審判部の仕事を思う時、いつも最初に思い浮かべるのは途方もない枠数の審判派遣表だ。毎年、数百にも及ぶ枠数が、日時・会場・カードとともに、まずは空欄で配信され、徐々に審判員の名前で埋まっていき、または全然埋まらず、ヒリヒリとキリキリとしながら、どうにかこうにか試合の日を迎える。そして実際に、一人ひとり生身の人間が、その何百という現場の派遣を埋めていくのだ。
2014年 関西学生ラクロスリーグ戦
2008年に資格をとってから日本を離れるまで150試合以上を吹き、そしてついにいま資格を失った、かつての末席審判員として、私はすでに「外の人」だから言える。これまで審判コミュニティを維持し続け、派遣表を埋め続け、リーグ戦という「場」を絶えず何十年も創出し続けていることは、本当に本当に偉業だと思う。審判員はもっともっと誇りに思っていい。そして、選手はもっともっとリスペクトを持った方がいい。あんな途方もないこと、毎年当たり前のように見えているかもしれないが、全く当たり前ではないのだから。
みんなのための遊び場を、仲間と作ってくれているのだから。
理事として向き合った、安全と未来:「現場のため」に下した猛暑対策の決断
さて、「場づくり」をする人として働いていたある日、思いがけず「理事にならないか?」とお話をいただいた。当時、私は名古屋在住の32歳。当然「なぜこんな凡庸な地方の若造に??」とかなり困惑したのを覚えている。しかし、悩んだ末、むしろそれが理由ではないかと考えるようになった。
私は「環境の手厚い私学や上位のチームの出身ではなく、女子の審判資格を持ち、僻地や下部の試合に駆り出され、本場関東が拠点ではない、地方の運営の現場を知っている、女子競技の経験がある若者」であり、そのどの面で切っても理事会ではマイノリティだが、その凡庸さこそ地方の現場ではマジョリティであった。
自分が多様性の象徴になるようなつもりはなかったが(それはさすがに僭越が過ぎる)、凡庸なりに理事の仲間入りをすることで、地方の「場づくり」にとって、現場にとって、いいことができればと思い、お話をお受けした。
2019年 会員総会にて。理事・監事・職員の皆さんと
理事になって最初に直面したのは、2018年の記録的な猛暑だった。この年の7月下旬、京都市で39.8℃を観測した日にマッチコミッショナーとして太陽が丘に派遣されていた私の執行部の後輩が、「死ぬかと思いました…」と報告を入れてきた。その数日後には気象庁が「命の危険があるような暑さ」「災害級の暑さ」という表現で会見を行い、世は騒然となった。当時、試合の催行可否基準には、猛暑による危険を想定したものはなく、運営マニュアルにも熱中症の人が出た場合の対処が述べられているに過ぎなかった。「猛暑によるリスクを、現場に背負わせたくない」と思った私は理事の先輩方に対して、高温時の試合の催行可否基準を作り、運営マニュアルに反映すべきではないかと提起した。
すぐに理事会で議論が始まり、当時はまだ一般的ではなく先進的考え方でもあったWBGT値31℃を基準とした運用が提案され、採用された。ちなみに、実はこの案に当初私はかなり反対だった。暑さによる中止が増え、消化できる日数が激減し、現場の運営の負担が大きく、そして選手が報われないのではないか、現場のために理事になったのに、それは避けたい、申し訳ないと思っていた。だが、何度問い直しても、最終的に、リーグ戦の安全に代えられるものはなく、今のこの結論に至る。
そうして運用が始まったこの年以降、猛暑の時間帯を避ける日程設定や、特定試合における対策など、JLAの熱中症対策は安全面でよりいい方向に充実していった。現場の負担増はどうしても避けられず今も葛藤は大きいが、日本の夏も年を追うごとに暑くなり、それでも対応は必要だったと振り返る。あの当時に自分が書いたマニュアルはいまもまだ現場で使われており、タフな運用をしながら安全な「場」を作っている現場に本当に感謝している。
コロナ禍で問い続けた「場」を繋ぐ意味
2020年、新型コロナウィルスが世界を襲った。不要不急の外出自粛が求められる中、私たちは議論した。ラクロスは不要不急なのか?どうやったらラクロスの「場」を繋げるのか?
当時、情報も整わず、世間はパニックで、医療ひっ迫によるリスクに加え、レピュテーションリスクも非常に高く、活動することでクラスターを発生させてしまうことは避けなければならなかった。一方で、そのまますべての活動をゼロにしてしまえば、ラクロスの「場」が将来にわたって失われていくこともまた大きなリスクだった。我々は、ラクロスの「場」を維持し未来に繋いでいくためには、ゼロリスクは求めないこと、ただし、リスクを負う覚悟をするからには、そのリスクを客観的に確認し、合理的な対策をしていこうと決めた。伴って、方針やガイドライン、リテラシーアッププログラムを作って、活動再開に進んだ。
そのさなかの2021年4月、友人が新型コロナウイルス感染症で亡くなった。クラブチームで4年間、毎週末ラクロスをして、一緒に過ごした仲間で、まだ36歳だった。
この頃、自分たちの判断が、全国のラクロスの現場のどこかで、人の生死に関わってしまうかもしれない、そんな底のない恐怖といつも隣合わせだった。このコロナ禍の3年間ほど、ラクロスをする「場」が当たり前ではないのだと痛感した日々はない。それでも仲間と何とか「場」を作り続けたあの日々は、きっと今に繋がっている。
あの頃、感染対策を徹底した一人ひとりの意識と行動が、今にラクロスの「場」を繋いできたのだとも思う。
未来の仲間たちへ:これからも、私たちは「場」を作っていく
2023年、本業で海外に赴任し、私は現場を離れた。日本では今日も当たり前のように、誰かがラクロスの「場」を作っている。
自分たちの遊び場を自分たちで。あるいは、みんなのための遊び場を仲間が。班員、班長、審判、連盟執行部、理事、いろんな立場で「場」を作っている。
日本のラクロスコミュニティは、ずっとそういう文化を紡いできた。
そして私たちは、2026年女子世界大会だって、2027年男子世界大会だって、これから仲間と自分たちで作るのだし、それはきっと未来の「場」に繋がっていく。このコラムを読んだ誰かが、そのために仲間となって、来年、再来年と。現場で一緒に働いてくれていることを、タイの地から願っている。
2022年 コロナ禍を乗り越えて。理事会オンサイトにて
Text:公益社団法人日本ラクロス協会理事 永田久美子
写真:本人提供